沖縄で海や星がきれいな理由は?独自の発展を遂げた食文化を知り、さらなる魅力を見つけよう
 INDEX
INDEX
 RECOMMEND
RECOMMEND- 【福井県坂井市】結婚×移住で育む家族のカタチ
- 【福井県坂井市】自治体主催の婚活イベント(移住促進&マッチングツアー)参加レポ
- 日本全国の地方自治体の首長にお話を伺う「日本全国首長対談」シリーズまとめ

沖縄の海
株式会社ブランド総合研究所が2021年に実施した「都道府県魅力度ランキング」で第3位に輝いた沖縄県。周囲は澄んだ海に囲まれており、東洋のガラパゴスと言われている「小笠原諸島」や、美しい星空を眺められる「西表石垣国立公園」などがあるため、毎年多くの観光客が訪れています。
今回はそんな沖縄の海や星が綺麗な理由や、独自の発展を遂げた食文化についてご紹介します。
文/鰆
大自然に囲まれた沖縄県
城山からの眺め
東京から飛行機で約2時間44分の場所にある沖縄県。人口1,462,940人(2022年4月時点)、面積2,281 km²の日本で4番目に小さい県です。かつては琉球王国という国であったため、日本となった今でも、王国時代の伝統芸能や食文化が根強く残っています。
現在は小さな離島が集まっている沖縄ですが、昔は中国大陸と陸続きでした。それが長い時間をかけて大陸から切り離されたため、元々中国大陸にいた生物たちは、沖縄の環境に合わせて独自に進化を遂げました。そのため県内にはイリオモテヤマネコやヤンバルクイナなど、沖縄にしか生息していない生物が数多く生息しています。
また沖縄周辺の海には約400種類のサンゴと熱帯魚が生息しており、海中にはまるで竜宮城のような華やかな景色が広がっています。
沖縄県の海はなぜ綺麗なの?
沖縄のサンゴ礁
東洋一美しいとされている「与那覇前浜ビーチ」のある沖縄。この項目では沖縄の海が綺麗な理由についてご紹介します。
黒潮海流に属しているから
沖縄の海が綺麗な理由として、黒潮海流に属していることがあげられます。黒潮海流とは日本列島に沿って流れる暖かい海流のこと。潮の流れが速く、水が濁る原因となるプランクトンや微生物などの生き物が少ないため、沖縄の海は澄み渡っているのです。
大きな川が少ないから
大きな川が少ないのも、沖縄の海が美しい理由の一つです。
海が濁る原因として、生活排水を含んだ川の水の流入があげられます。生活排水に含まれるリンや窒素が、海を濁らせるプランクトンの増殖を引き起こすからです。しかし、複数の島が集まっている沖縄には、大きな川がほとんど無いため、生活排水が海に流れにくく、美しい水質が保たれているのです。
サンゴ礁に囲まれているから
海の中に約400種類のサンゴが生息しているのも、沖縄の海が綺麗な理由の一つです。
サンゴとは、イソギンチャクやイソギンチャクの仲間である「刺胞動物門花虫鋼」に属する動物のこと。体内には光合成を行う植物プランクトンの仲間である「褐虫藻」が住んでいるほか、骨格が石灰質でできているため、動物と植物、鉱物の3つの特徴を持つ不思議な生物でもあります。
そんなサンゴが長い年月をかけて積み重なってできた「サンゴ礁」は「海のオアシス」と呼ばれています。サンゴ礁は海の生物のエサ場や住み処、産卵場所となるからです。実際海の生き物の約25%はサンゴ域で生活していると言われています。
そのため、沖縄の海はさまざまな海の生き物たちが生息する美しい環境が保たれているのです。
沖縄県の星が美しいと言われる理由とは?

石垣島の天の川
国際ダークスカイ協会が認定する「星空保護区」に日本で初めて選ばれた「西表石垣国立公園」を持つ沖縄。この項目では沖縄の星が美しい理由について解説します。
まちの明かりが少ないから
沖縄の星が美しいと言われる理由として、星の光を遮るまちの明かりが少ないことがあげられます。
人間の目は暗い場所でも明るい場所でも目が正常に働き続けるために、「明順応」「暗順応」という働きが行われます。
明順応とは、暗い場所から明るい場所に移動した際、時間の経過とともに視力が明るい場所に適応する働きのことです。例としては地下鉄や映画館から外に出たとき、一瞬目がくらんでから明るい外の景色がはっきりと見えていくような状態があげられます。
一方、暗順応とは明順応とは逆で、明るい場所から暗い場所に移動した際、暗い場所でも視力が働くような状態になることを指します。例としては部屋を暗くした際に、最初は何も見えない状態であったのに、時間がたつと部屋に置いてある家具や壁が見えてくるような状態です。
前述の理由で、まちの明かりが少ないと目が暗順応の状態になり、より星空が鮮明に見えるようになるのです。
ちなみに「星空保護区」に指定されている八重山諸島の「西表石垣国立公園」の空の暗さは、星空保護区に認定されるための基準値である21.2 mag/arcsec²を上回る21.62〜21.99mag/arcsec²であることが明らかになっています。
偏西風の影響が少ないから
瞬きの少ない、まるで写真のような星空が見られる沖縄。その理由として、県が偏西風の中で特に風速の早い「ジェット気流」の影響を受けづらい場所にあることがあげられます。
星空が瞬くのは、地球を覆う空気の層である「大気」の温度が変化して、空気の密度が変わるのが原因です。なぜなら光は空気の密度が変わり折れ曲がって見えるからです。例えるのであれば、穏やかな水面では上空の景色が鏡のように映るのに対し、波風の立った水面には、景色がゆらゆらと揺れて映るのと同じような状態です。
しかし沖縄県はジェット気流の影響が少なく、大気が安定しているため、瞬きが少なく、くっきりとした美しい星々が見られるのです。
見られる星座の種類が多いから
本州付近では一年を通して、全88星座の内、60種類程度の星座を観察できます。しかし沖縄は南半球と北半球の星座が両方見える場所に位置しているため、普段日本ではなかなか見られない以下の星座を含む、83種類もの星座が観察可能です。
■みなみじゅうじ座
日本では沖縄と小笠原諸島でしか見られない南天の代表的な星座。
12月〜6月頃に見られる。
■ケンタウルス座
上半身が人間、下半身が馬である「ケンタウルス」をかたどった星座。日本では全体の全体の半分程度しか観察できないが、沖縄では星座の全体が見られる。春の終わりから初夏にかけてが見頃とされている。
沖縄独自の食文化をご紹介

ゴーヤーチャンプル
1872年まで琉球王国という国であった沖縄県。中国や東南アジア、朝鮮、日本と盛んに外交や貿易を行っていたため、さまざまな国の文化の影響を受けた独自の食文化が残っています。
この項目では、そんな沖縄の食文化についてご紹介します。
豚肉料理が多い
元々琉球王国時代中国の使節団である「冊封使」の食料として献上されていた豚。中国から芋の栽培が伝わり、廃棄する芋の茎や葉を飼料にできるようになってから、盛んに飼育されるようになりました。しかし第二次世界大戦頃まで庶民の間では、高級品であったため、限られた豚肉をあますことなくおいしくいただくために、沖縄では以下のような豚肉料理が編み出されました。
■アシティビチ
醤油等で味付けした骨付きの豚足を柔らかくなるまでじっくり煮込んだ料理。コラーゲンたっぷりで、ぷりぷりとした食感が楽しめる。
■あぶらみそ
豚肉とみそ、しょうが、泡盛などを一緒に炒めたもの。ごはんに乗せたりおにぎりの具にしたりして食べる。
■中身汁
豚の内臓をカツオベースのスープで煮込んだ料理。しょうがと青ネギをかけて食べる。
■ラフテー
皮付きの豚バラ肉を、泡盛や醤油で煮込んだ料理。
首里城で食べられていた宮廷料理
薩摩藩から琉球を統治するために派遣された在番奉行や、中国の冊封使をもてなす際に作られていた宮廷料理。のちに上流階級に伝わり、明治以降には一般家庭にまで広がり発展しました。
代表的な宮廷料理として、「東道盆(とぅんだーぶん)」があげられます。東道盆は、30種類以上のコース料理である「五段御取持(ぐだんのうとぅいもち)」の中の、酒のつまみを担当するオードブルのような料理のことを指します。同名の琉球漆器に料理が詰められていることからその名前が付けられました。見た目が美しく冷めてもおいしくいただける、以下のような料理が入っているのが特徴です。
■シシかまぼこ
豚挽肉と魚のすり身をまぜて作ったかまぼこ。沖縄の最上級かまぼこと言われている。
■ミヌダル
煎った黒ごまに泡盛や砂糖、醤油などをまぜたものを豚の肩ロース肉に塗って焼いたもの。
見た目が真っ黒なためクロジン(黒肉)とも呼ばれている。
■花イカ
甲イカに切り込みを入れてゆで、食紅でいろを付けたもの。花のような華やかな見た目が特徴。
H3:各家庭で親しまれている庶民料理
薬で治療するのもバランスの取れた食事をとるのも、命を維持するために両方かかせない「医食同源」という考え方が中国から伝わった沖縄。
そんな場所に住む庶民の間では、貧しい暮らしの中で健康を維持するための以下のような料理が編み出されました。
■ゴーヤーチャンプルー
ゴーヤと卵、豆腐などを一緒に炒めたもの。ゴーヤには人の健康を維持する働きのあるビタミンが豊富に含まれている。またゴーヤには、食欲増進作用があるため、暑い夏が続く「亜熱帯海洋性気候」に属する沖縄で、夏バテするのを防いでくれる。
■いか墨汁
イカと豚肉、青汁の原料にもなっている「ニガナ」を煮込み、イカ墨を加えたもの。ニガナは琉球王朝時代から薬草として使用されており、カルシウムやビタミン、ポリフェノールなどの栄養が豊富に含まれている。
■ウム二ー
島野菜の紅芋を砂糖と一緒に煮てつぶしたもの。紅芋には食物繊維や肌の老化を防ぐと言われているビタミンCが豊富に含まれている。田畑で仕事をする際にも持って行かれていた。
沖縄の自然や文化を知って、さらなる魅力を見つけよう

沖縄の美しい海
今回は沖縄の海や星が綺麗な理由や沖縄の食文化についてご紹介しました。
大きな川が少なく、黒潮海流が流れているおかげでクリアに保たれている沖縄の海。ジェット気流の影響を受けづらい場所にあり、まちの明かりが少ないおかげで瞬きの少ない写真のような星空が広がる沖縄の夜空。こうしてさまざまな条件が重なることで、沖縄の美しい自然は形作られているのです。
また、琉球王国時代に中国や日本をはじめとする諸外国と外交を重ねる内に、独自の食文化が生まれた沖縄県。かつて首里城で食べられていた宮廷料理も、貧しい暮らしの中でも健康に暮らしていこうと考案された庶民料理も、沖縄の家庭の味として脈々と受け継がれています。
「沖縄の自然に触れたい!」「沖縄料理を食べてみたい!」という方は、ぜひ旅行や移住のために沖縄を訪れてみてはいかがでしょうか。
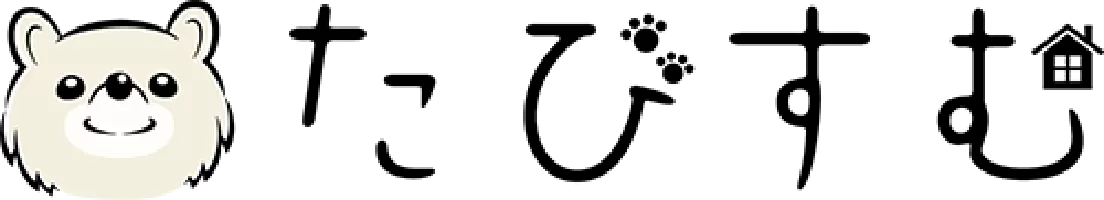
 ツイート
ツイート
 シェア
シェア
 はてなブックマーク
はてなブックマーク
 コピー
コピー






